売れない時、作品そのものを「もうダメかな」と思ってしまうこと、ありますよね。
でも、少しだけ“見せ方”を変えただけで、反応が変わったことが何度かありました。
今回は、作品を変えずにできた小さな工夫を3つ紹介します。
あわせて読みたい

写真の「並べ方」を変えてみた
最初の1枚を“使っているイメージ”に

作品の第一印象を決めるのは、一覧ページに表示される最初の1枚です。
ここで使用シーンが伝わる写真を選ぶことで、購入者の目に留まりやすくなります。
たとえば、バッグなら実際に手に持ったり、椅子の背に掛けたりして撮るだけで「サイズ感」や「生活の中での使い方」が伝わります。白背景の写真も大切ですが、あくまで補足的に。
お客様は自分の暮らしに置き換えて想像したいのです。使っている姿を見せることで、購入の決め手になることも。まずは1枚目から、暮らしに馴染むイメージを意識してみてください。

“持った感じ”が見えるだけで、反応が全然違いました。
2枚目・3枚目に“比較”や“裏側”を入れる
2枚目・3枚目には、サイズ比較や裏側などの“情報補完になる写真”を入れるのがおすすめです。
というのも、お客様が購入をためらう理由の多くは「よくわからないから」。
たとえばバッグなら、内側のポケットや裏地の仕様、ほかのアイテムと並べたサイズ感などを見せることで「自分に合っていそうか」が判断しやすくなります。
わたしは、A4ノートや500mlのペットボトルと並べた写真を追加したり、サイズ展開している物を並べたりサイズの違いを見て分かるようにしました。
表から見えない部分や他アイテムとの比較は、お客様の“見えない不安”を解消するための鍵です。
1枚目で惹きつけたら、次は“安心できる情報”を丁寧に届けましょう。
説明文の「冒頭」をお客様の目線に
「わたしが使ってみて感じたこと」から始めた
「わたしが使ってみてどう感じたか」から説明文を書き始めると、お客様の反応が明らかに変わりました。
スペックや素材の説明よりも、まず“使う場面”を伝えることで、読み手が自分ごととして想像しやすくなるからです。
たとえば「A4が入るトートバッグ」とだけ書くより、「お弁当と水筒がすっと入って、買い物にもそのまま持って行けます」と書いたり、日常の風景が思い描けるような書き方の方が伝わりやすいです。
作り手としてのリアルな視点は、“ちょっとした使いやすさ”や“嬉しいポイント”にも目が届きます。
お客様にとっては、その一言が購入の決め手になることも。
写真撮影についてはこちらの記事でも紹介しています

サイズや素材の説明ももちろん大事ですが、まずは「実際にどう使えるか」から伝えることで、
商品の魅力がより伝わりやすくなりました。
「○○にお困りの方へ」と悩みを拾った一文
説明文の冒頭に「○○でお困りではありませんか?」という一文を加えるだけで、
お客様の反応がぐっと良くなりました。
なぜなら、読者が「これ、自分のことだ」と感じてくれるからです。

“わたしのことかも”って思えるだけで、読みたくなるんですね。
たとえば、ただ「コンパクトなバッグです」と書くよりも、
「ちょうどいいサイズのバッグが見つからない方へ」と始めることで、
「まさにそういうのが欲しかった」と共感してもらえる確率が高くなります。
また、「財布とスマホだけ持って出かけたいときにぴったり」と書いたことで、
探していたバッグはこれだと感じてもらいやすくなりました。
お客様は今抱えている悩みを少しでも解消できる商品を、常に探しています。
共感を呼ぶ入り口があると、商品説明が“自分に必要なもの”として読まれやすくなります。
サイズや仕様に入る前に、まずお客様の困りごとに寄り添うひと言を添えてみてください。
カラーやサイズ展開を「伝わるように整理」

色名だけでなく“雰囲気”で伝える
カラーの名前だけでなく、“雰囲気”を言葉で補足することで、商品の魅力がより伝わるようになります。
色名だけでは、製作者とお客様の間にイメージの差が生まれやすく、
それが結果としてクレームにつながることもあるため、色を丁寧に伝えることはとても重要だと感じています。
たとえば、「グレージュ×カーキベージュ」のバッグの場合、
商品名にはそのままの色名を記載しますが、説明文では
「くすみがかったグレーに、落ち着いたベージュを合わせた配色。通勤スタイルにも自然に馴染みます。」
といった一文を添えることで、着る服や場面をイメージしやすくなり、
「これなら普段づかいにも合いそう」と感じていただけます。
お客様は、「この色、自分に合うかな?」と不安を感じながら選んでいます。
そんな時こそ、色が持つ印象や雰囲気を丁寧に伝えることが、購入の後押しになります。
特にオンライン販売では、“伝えすぎるくらいでちょうどいい”のかもしれません。
色の説明は、イメージと言葉の両方で届けることを意識しています。
サイズの“感覚”を補足する
サイズ表記に“感覚的な説明”を加えることで、お客様の不安がぐっと減りました。
数字だけでは伝わりにくい部分を、具体的な使用例で補うことで、想像がしやすくなるからです。
たとえば、「縦30cm×横25cm×マチ13cm」とだけ書いていた頃は、
「実際どれくらい入るの?」と不安に感じられることが多くありました。
そこで、「500mlの水筒とお弁当箱がすっきり入るサイズ感です」
「A4のファイルが縦にすっぽり入ります」などと補足するようにしたところ、
「イメージが湧きました」「思っていたより大きくてちょうどよかった」
といったレビューをいただけるようになりました。
お客様の多くは、サイズ感に不安を感じています。
特に通販では“思っていたのと違った”というすれ違いが起こりがちです。
数字に加えて、暮らしの中のモノでたとえるだけで、伝わり方は大きく変わります。
サイズは“測る”だけでなく、“感じてもらう”意識で書くことが大切だと実感しています。
作品を変えなくても、変えられることはある
売れない時期は、作品そのものを否定したくなります。
でも、“見せ方”を見直すことで、お客様の印象は変わります。
まずは1つ、写真や説明文を見直すところから始めてみませんか。

小さな工夫でも、“伝わり方”は大きく変えられますよ。
他にも、販売時の迷いについて書いた記事があります
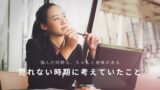
まとめ
オンライン販売では、実物を手に取って確認できないからこそ、
「色」や「サイズ」をどう伝えるかがとても大切です。
色の印象やサイズの感覚を、ただの情報としてではなく、
お客様の“想像”に届くような言葉で補ってあげること。
それが、安心して購入してもらうための小さな工夫になります。
特別な表現でなくても大丈夫です。
「この色はどんな雰囲気か」「どんな場面で使えるか」
「どれくらい入るか」を、暮らしの中の言葉で伝えてみてください。
そのひと手間が、きっとお客様の背中をそっと押してくれます。


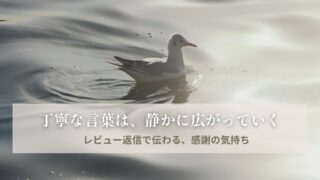
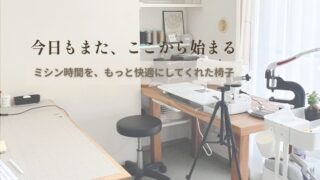
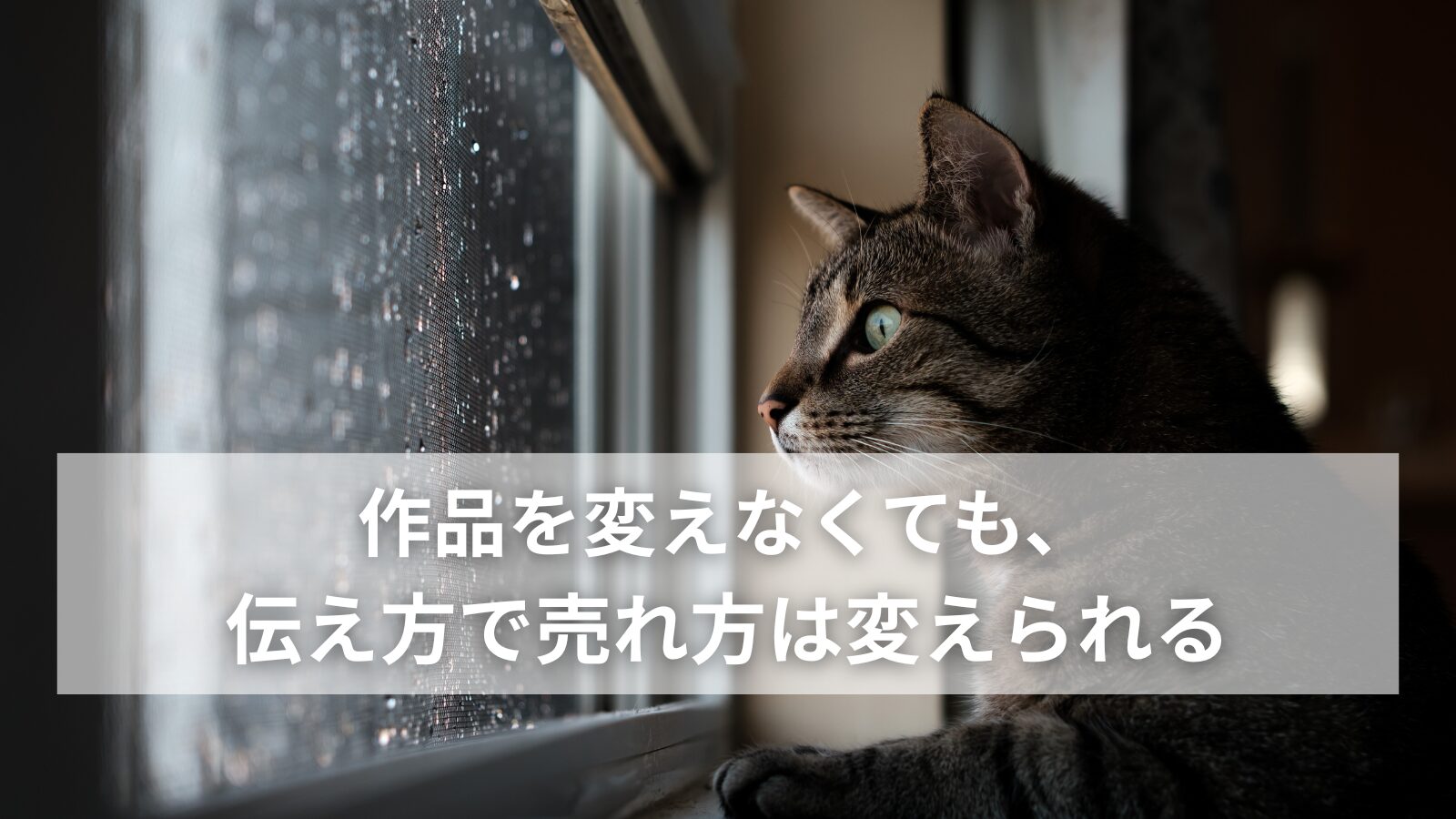


コメント