ハンドメイド作品の制作には、「しっかり計画を立てて進める」という方も多いと思います。
でも私の場合は、いつもきっちり決めてスタートするというより、「そろそろ新作を出そうかな」と思い立ったり、ふとした瞬間にバッグのアイデアが浮かんだり。そんなゆるやかな始まり方が多いです。
そこから、試作して、使ってみて、作り直して…と、少しずつかたちにしていく流れが、私にとっての“商品化”の道のりです。
この記事では、そんな私自身のやり方で進めている「新作ができるまで」の流れをご紹介します。
これからハンドメイド販売を始めたい方や、新作づくりに迷っている方の参考になれば嬉しいです。
まずはアイデア出しとイメージ固めから
まずはリサーチ。最近の傾向をざっくり把握
新作づくりのはじめに、まず行うのはリサーチです。
使いたい生地が決まっているときは、検索窓に「生地名+〇〇バッグ」と入力して、出てくる商品をざっとチェックします。
すると、最近の傾向がなんとなく見えてきます。

“生地名+バッグ”で検索してみると、意外と参考になるんです!
たとえば、大きめバッグが多いのか、小さめが人気なのか。持ち手は細めか太めか、長さは肩掛け仕様が多いかなど、形やスタイルの流行がつかめます。
そのあと、年齢層や用途(仕事・普段使い・旅行など)に合わせて検索条件を絞っていくと、自分が作ろうとしているアイテムとの方向性のすり合わせができます。
また、ヒントになるのはリサーチだけではありません。
お客様とのメッセージのやりとりの中で、「もう少し小さいサイズもあれば…」「縦長だと入れたいものが入らない」など、サイズのバリエーションに関するご要望をいただくこともあります。
そうした言葉は、新作づくりのアイデア源としてとても貴重です。
流行やニーズを把握しつつ、自分らしさも大切にしながら、制作の方向性を少しずつ固めていきます。
理想の使い方や持ち主像を考える
メモしたアイデアの中から「これを形にしたい」と思えるものが出てきたら、次に考えるのが「誰が、どんな場面で使うか」ということ。
これは、デザインやサイズ感、使い勝手を決めるうえで大切なヒントになります。
たとえば、「お仕事用にも使えるトートバッグを作りたい」と思ったとき。
私のショップでは、“シンプルできれいめな服が好きな大人の女性”をイメージしているので、カジュアルすぎないデザインや落ち着いた色合いを選ぶようにしています。
「書類が入ること」「肩にかけられること」「見た目がすっきりしていること」など、使うシーンを想像することで、自然と必要な機能が見えてきます。
また、「このバッグを持って出かけたくなるかな?」「職場でも浮かずに持てるかな?」と、自分自身にも問いかけてみます。
持ち歩く姿を思い描いて、ワクワクできるかどうかも大切な判断基準です。
“どんな人に、どんなふうに使ってほしいか”。
それを明確にしておくことで、ぶれのない作品づくりがしやすくなります。
試作を通して、形やサイズ感を確認
まずは簡易的に直断ちで試してみる

イメージが固まったら、まずは形にしてみます。とはいえ、いきなり完成品を作るわけではありません。
私は「直断ち(型紙なしで直接裁断)」でざっくりとした試作を作ることが多いです。
この段階では、見た目のバランスや全体の雰囲気をざっくり確認するのが目的です。
多少のゆがみやズレは気にせず、縫い代も適当に取ってとにかく“形にしてみる”ことを優先します。
頭の中では良さそうに思えても、実際に縫って立体にしてみると「なんだか縦長すぎる?」「底が広すぎるかも?」といった違和感が見えてくるからです。
この“とりあえずやってみる”という工程を挟むことで、完成度の高い作品に近づけやすくなります。
布の厚みや質感によっても印象は変わるので、まずは簡単にでも形にしてみることが大切だと感じています。
実物で使い勝手を試すことで見えてくる課題
ざっくりとした試作ができたら、実際に荷物を入れて使ってみます。
この工程で、「見た目はいいけれど使いにくい」と気づくことが意外と多いのです。
たとえば、「ペットボトルが入ると思ったけれど取り出しにくい」「肩掛けできる長さのはずが、厚手の服では窮屈だった」など、実際に使ってみて初めて気づく点がたくさんあります。
また、全体の重さや生地のたわみ具合など、写真や図ではわからない“感覚的な使い心地”も重要なチェックポイントです。

見た目はいいのに…って、使ってみて初めて気づくこと多いですよね
私は鏡の前で持ってバランスを見たり、想定する荷物を入れてシワやたわみ、底の強度などをチェックします。
「重みで変なシワが出ないか?」「バッグ口が崩れすぎないか?」「底がたわまず安定しているか?」と、実際の使用シーンを思い描きながら、いろんな角度から確認するようにしています。
こうして“使い勝手”に目を向けることで、見た目だけでなく、長く使いたくなるバッグへと仕上げていくことができます。
修正と調整をくり返してブラッシュアップ
パターンの引き直しは何度でも
試作を使ってみて気になる点が出てくると、私は何度も型紙を引き直します。
「もうちょっと高さを出したい」「底の形が丸すぎるかも」といった違和感をそのままにしておくと、後で“なんとなくしっくりこない”作品になってしまうからです。
特に、画面越しで見たときの印象や、実際に手に持ったときのバランスはとても大事にしています。
自分の中で「これは出していい」と思えるまで、パターンを修正しては縫い直し…をくり返すことも珍しくありません。
実際、少しのサイズ差やラインの角度を変えるだけで、ぐっと洗練された印象になることもあります。
完成形が見えないうちは遠回りに感じるかもしれませんが、この“引き直しの積み重ね”こそが、自分らしい作品を作る近道だと思っています。

一度の修正じゃ終わらないのが私流です…(笑)
素材選びやパーツの印象も見直し
本体の形が決まってきたら、次は素材やパーツの見直しにも目を向けます。
「
同じデザインでも、生地や金具ひとつで印象がガラッと変わる」――これは制作を重ねる中で実感してきたことです。
たとえば、帆布の厚みや質感によって、仕上がりの雰囲気がカジュアル寄りにも、きれいめにもなります。
持ち手の幅や長さ、金具の色やサイズ、ステッチの入れ方など、細かな部分が全体の印象を左右することも多いです。

私はこの段階で、いくつかの組み合わせを試して、しっくりくるものを探すようにしています。
「この幅の持ち手だとごつく見えるかな?」「カシメは目立たせるか、さりげなくするか」など、仕上がりのバランスを見ながら細かく調整します。
見た目の雰囲気だけでなく、使いやすさや持ちやすさにもつながるポイントなので、素材選びやパーツの選定は“最後のひと押し”としてとても重要な工程です。
販売前の準備とお披露目の工夫
撮影と説明文で世界観を伝える
販売前の最後の仕上げとして欠かせないのが、写真と商品説明文です。
どちらも、ただ情報を伝えるだけでなく、その作品の雰囲気や“使うシーン”を想像してもらうための大切な要素です。
写真では、自然光のもとで色が正しく伝わるように気を配りながら、背景や余白の取り方にも注意しています。
全体・側面・内側・持ったときの雰囲気など、いろんな角度から撮ることで、サイズ感や質感をしっかり伝えられるように意識しています。
説明文では、サイズや素材などの基本情報はもちろん、「どんな方におすすめか」「どんなシーンで活躍するか」を具体的に書くようにしています。
たとえば、「A4サイズの書類がすっきり入る」「肩にかけても収まりのいい長さ」など、実際の使用イメージが湧くような言葉を心がけています。
ひとつひとつ手作りしているからこそ、写真と文章で“伝わる工夫”をすることが、お客様との信頼につながっていくと感じています。
▼写真の明るさや構図の工夫についてはこちらで紹介しています

▼商品の魅力を伝える文章について詳しくはこちら


SNSでの見せ方・反応を見ながら販売へ
作品が完成したら、販売ページに載せる前に、SNSで少しずつ公開していきます。
いきなり“完成品”を発表するのではなく、制作の途中や試作段階の様子をシェアすることで、「どんなものができるんだろう?」「こんなふうに作っているんだ」と、お客様に興味を持っていただけるよう意識しています。
たとえば、「サイズ感に迷ってます」「この形、使いやすそう?」といったリアルな制作の過程や悩みを投稿すると、フォロワーさんから反応が返ってくることも。
そうしたやり取りの中に、実はヒントやニーズが隠れていることがあります。
完成が近づいたら、写真や動画で作品の全体像を紹介します。
「このあと◯時から販売予定です」と事前にお知らせする方法もありますが、私は今のところ、少し別のスタイルで進めています。
というのも、以前からショップをフォローしてくださっている方に、いち早く新作を見ていただけたら嬉しいなと思っていて、まずはショップに公開し、その後にSNSでお知らせしています。
数量限定の商品ではないので、今はこの流れが自分に合っているように感じています。
SNSでの事前告知については、人によって感じ方もスタイルもさまざまです。
「やってみたいけれどちょっと苦手…」という声も耳にしますし、積極的に取り入れている方もたくさんいます。
どちらが正解というわけではなく、自分に合った方法を見つけることが何より大切だと思います。
無理なく続けられて、気持ちよく発信できるやり方を選べば、それがその人らしいスタイルになります。
いずれにしても、SNSでの発信は、作品を届けるうえで欠かせない大切なステップのひとつです。

SNSで発信するって、ちょっと勇気いりますよね
▼こちらでも、新作の出し方について書いてます。

まとめ|自分らしい新作づくりのペースで
新作を商品化するまでには、リサーチから試作、修正、撮影、販売まで、いくつもの工程があります。
きっちり計画を立てて進める方もいれば、私のように「なんとなく作りたくなって始まる」タイプもいます。
どのステップも正解があるわけではなく、自分のスタイルに合ったやり方を見つけていくことが、長く続けるためのコツだと感じています。
たとえ遠回りに思えても、試作を重ねたり、SNSでのやりとりからヒントを得たりすることで、納得のいく一品に近づいていきます。
ひとつの作品が形になるまでの過程そのものが、ハンドメイドの楽しさでもあります。
焦らず、自分のペースで。
「これだ」と思える新作が生まれるまでの道のりを、これからも丁寧に歩んでいきたいと思います。
▼家事と両立しながら制作時間をつくる工夫も書いています



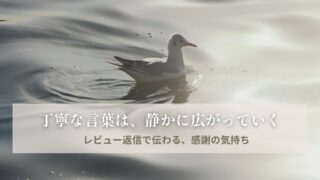
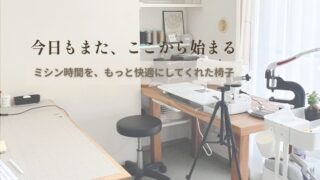



コメント